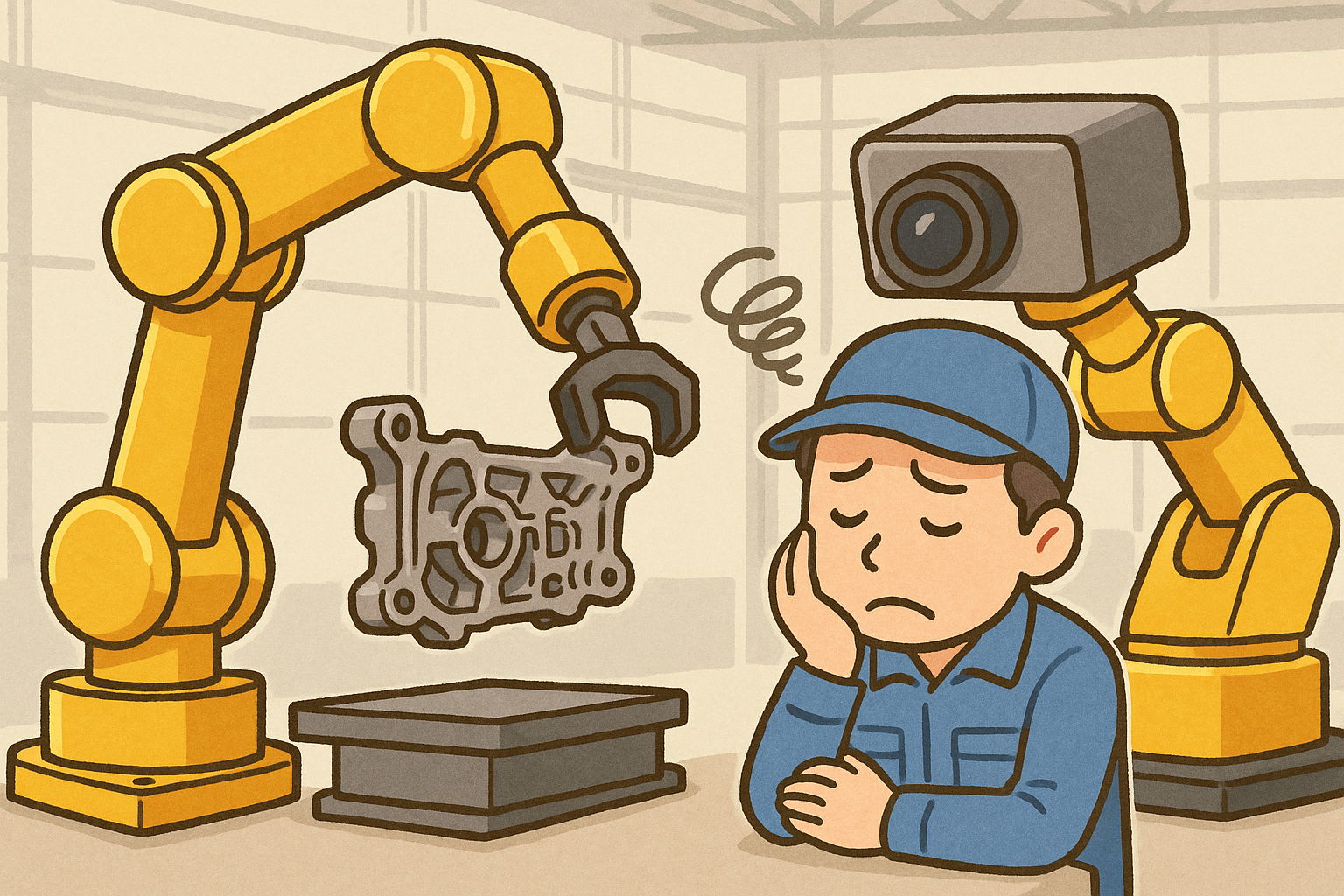機構設計の特徴
従来のダイカスト製品向け外観検査装置では、製品全体を検査するために、製品を吊り上げて撮像する構造や、反転機構を備えた大型ロボットを必要とするものが一般的でした。また、検査の高速化を図るために複数台のカメラを同時に稼働させる方式も採用されてきましたが、これらはいずれも装置構成が複雑かつ大規模となりやすく、導入時の初期投資が高額になる傾向がありました。さらに、多くの場合、それぞれの装置は特定の製品に最適化されており、他の製品への柔軟な対応が困難であるという制約も抱えていました。
こうした課題に対して、IVI-360™は汎用性をコンセプトに開発されました。本装置は、6軸ロボットアームと回転ステージにより、製品を反転させる機構を不要とし、7自由度のロボット制御を行っています。
本装置の中核をなすのは、サーボモータで制御されるリング状の回転支持台です。被検査物の下部は開口構造となっており被検査物を回転させながら、移動自在なカメラで製品の上面と側面だけでなく、下面側からの撮像も可能です。また、カメラの側面に緑・赤の2色マーカーホルダを備え、合否の結果を安価にマーキング。不良品の取り違えリスクを低減します。
また、アルミダイカスト製品の外観検査に特化するにあたり、適切な画素密度と撮像条件を選定することで、演算負荷を抑えつつも実用に十分な検出精度を確保しています。
この構成により、導入コストの大幅な低減が可能となったほか、製品ごとの治具交換による柔軟な対応も実現しています。さらに、ユーザー自身が製品ごとの検査条件を追加・変更でき、1台の装置で複数種の製品に対応する柔軟性を持たせることが可能です。
※本技術は株式会社第七機械設計の特許技術(登録第7750589号/JPO: P7750589)です。AIソフトの特徴
学習の中身を「見える化」する技術
IVI-360™に搭載されたAIエンジンは、ダイカスト製品の不良をただ分類するだけでなく、「AIが何をどのように覚えているか」をグラフで見えるようにする仕組みを持っています。
これまでのAI判定では、「正解率」や「検出率」などの数値だけでモデルの良し悪しを評価していました。しかし、たとえば「湯じわ」といっても、波のように浅く広がるものもあれば、深くはっきりとした形もあります。これらを一括で「NG」と学習させても、AIが十分に理解できないことがあります。
IVI-360™では、まず検査画像から不良の特徴(パターンや模様)を数値として取り出します。これを「第1特徴ベクトル」と呼びます。その中から、判断に役立つ20項目ほどの代表的な数値(第2特徴ベクトル)を選び出し、それをグラフで表示します。
たとえば、
・湯じわ → なめらかな波のような線
・打痕 → 突き出たトゲのような線
・汚れ → 不規則で揺れた線
というように、不良ごとに線の形が変わるため、AIの「見え方」を視覚的に確認できます。
さらに、OK品とNG品の線を色分けして表示することで、今見ている製品がどのグループに近いかが一目でわかります。これにより、判定に迷う製品や、軽微な不良も見逃しにくくなります。
また、AIが間違えたときも、グラフを見ることで「特徴の取り出しが不足しているのか」「しきい値の設定に問題があるのか」を判断できるため、再学習や調整がしやすくなります。
この技術は、AIを単なる自動判定ツールではなく、「人と一緒に考えるパートナー」として活用するというIVI-360™の考え方に合致しています。現場のエンジニアが納得して使える、信頼性の高いAI判定を実現します。
※本技術は、株式会社 Roxyの特許技術(特許第7309134号 / JPO: P7309134)です。